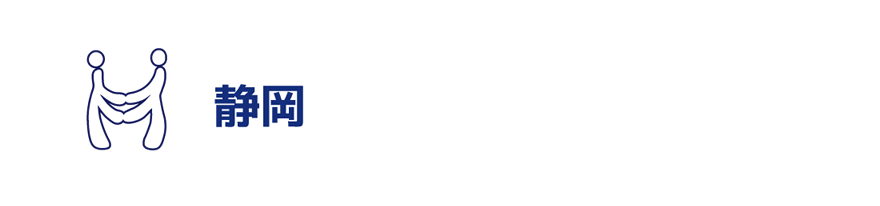1.本土における地上戦準備
1-1 兵力動員計画 ―根こそぎ動員―
 山田朗『本土決戦の虚像と実像』より
山田朗『本土決戦の虚像と実像』より
1944年7月、日本の占領地であったサイパン島がアメリカ軍の手に落ち、それにつづくレイテ決戦でも日本の連合艦隊は壊滅し、陸軍も約8万人の兵力を失って大敗した。
こうして「絶対国防圏」が崩壊したため、大本営は1945年1月、「本土決戦」の構想を初めて明文化した「帝国陸海軍作戦計画大綱」を打ち出した。アメリカ軍が秋までに本土に上陸するという判断のもと、それまでに本土と朝鮮半島における「本土決戦」準備を終わらせることが明示され、小笠原や沖縄はそのための時間稼ぎと位置づけられた。陸軍においては、地域ごとの抗戦と自活を図るための作戦軍である「方面軍」の編成替えがなされた。
4月、大本営は「決号作戦準備要綱」を発令した。これにより本土決戦を正式に「決号作戦」と名づけた。地域別に決1号から決7号作戦まで構想され、アメリカ軍主力の上陸地として想定した関東を決3号、九州を決6号作戦とした。上陸を10月以降と想定し、海軍は沿岸部での特攻部隊の出撃基地建設を、陸軍は「国土築城実施要綱」を発し、沿岸部や内陸部に防御や攻撃のための陣地構築を急いだ。3月に政府が制定していた「軍事特別措置法」により、国民の土地・建物を管理・使用・収用し、軍事施設の新設や拡張を行った。
他方1月の時点で、陸海軍の主力は中国大陸・東南アジア・太平洋の島々にあり、本土を守る兵力は乏しかった。そこで、150万人の動員が計画され、3次にわたって根こそぎ動員が行われた。その結果、新たな編成を加え、陸軍は64個師団、300万人近い兵力を本土と朝鮮に確保した。行政面では、全国を8個のブロックに分け、それぞれに地方総監府を設置して、地方行政との連携を緊密にさせ、本土が分断された場合でも、戦争が継続できるようにした。
 山田朗『本土決戦の虚像と実像』より
山田朗『本土決戦の虚像と実像』より
1-2 労働力動員計画 ―国民義勇隊―
1945年3月、政府は全ての職場・学校・地域で「国民義勇隊」を組織することを閣議決定する。義勇隊は国民学校初等科修了(現在の小学校卒業)以上65歳以下の男子と45歳以下の女子から構成された。防空、空襲被害の復旧、警防・食料増産活動などの従事者として、また軍事施設の建設など陸海軍の作戦準備に協力する軍隊の補助要員でもあった。義勇隊や学生は沿岸部や内陸部の陣地構築などの土木工事に動員された。しかし、多くは資材不足のため敗戦時には未完であった。また、空襲時の延焼を防ぐため事前に民家を壊しておく「建物疎開」にも動員された。
沖縄が制圧された6月、「義勇兵役法」が制定・公布され、義勇隊は「本土決戦」時には戦闘隊に転化して軍の指揮下で武器をとって戦うことになった。15歳以上 60歳以下の男子と17歳以上40歳以下の女子は全て「義勇兵」となり、「国民義勇戦闘隊」が組織される。その数は2,800万人にのぼり、在郷軍人などを指導者として竹槍訓練などが繰り返された。
2.静岡における状況
2-1 最前線の兵士たち ―沿岸配備師団 「護古部隊」―
1945年春以降、静岡も全県が「本土決戦」の基地・陣地と化していた。
陸軍については、第1総軍の下、軍隊の移動に困難がともなう薩埵峠付近を境に、東(決3号作戦地域)を第12方面軍と隷下の第53軍が、西(決4号作戦地域)を第13方面軍と隷下の第54軍が指揮を執っていた。この時点では、アメリカ軍が1946年春までに関東(相模湾・九十九里浜)に上陸し、その一部は東西の交通路の遮断と航空機基地獲得のために浜松と清水(のち御前崎)に上陸すると予想していた。
県下には58,800人以上の地上軍が配備される計画があった。まず、2月の第1次兵備(根こそぎ動員)で新設された第143師団(通称「護古部隊」)が浜松地区(歩兵第409連隊・第411連隊・第412連隊)と清水地区(歩兵第410連隊)に配備され、「敵の主上陸を遠州灘正面(浜名湖~天竜川の間)と予想し、之を水際に撃滅するため」に横穴陣地の設定に励んでいた。「護古(ごこ)」とは「名古屋を護る」という意味である。師団司令部は井伊谷村に置かれ、兵力は17,000名とされた。護古部隊は、上陸してきたアメリカ軍を沿岸部の陣地帯で拘束して消耗させることを目的とする歩兵が主力の沿岸配備師団だった。しかし、老兵と若年兵がほとんどで、兵器はおろか軍靴さえも行きわたらず、決戦部隊というには程遠かった。銃剣は全兵力の50%、火砲70%、小銃80%、通信機類30%、機銃30%強、弾薬糧食は半会戦分というみじめさである。部隊の持久・後退も許されず、「守地即死地」の「はりつけ師団」だった。
海軍もまた、アメリカ軍の上陸を阻むために、特攻艇の出撃基地を沼津・江ノ浦、清水・三保などに設置していた。
静岡県下に配備された陸軍地上部隊(1945年8月)
『静岡県史 通史編6 近現代二』より

本土決戦部隊系統表(静岡県に関連し、かつ主要なもののみを記載)
『静岡県史 通史編6近現代二』より

2-2 清水地区における陣地構築 ―有度村の「護古22254部隊」―
三保飛行場のある清水には、第143師団隷下の歩兵第410連隊(護古22254部隊)が配備され(4月6日編成完結)、日本平のある有度山で「本土決戦壕」の構築を始めていた。陣地設定は大隊単位で行われた。連隊長は松井利生大佐であった。有度国民学校(現清水有度第一小学校)に連隊本部が置かれていたという。
兵士たちは学校、寺、倉庫、旅館等に駐屯して壕を掘った。各自のノルマがあり、交替で掘り進めた。証言によると、軍靴が泥だらけになり、履いていられなくなることもあるので、藁草履が支給されることもあったようだ。壕の目的・用途については、「上陸する敵の戦車に爆弾を抱いて突っ込む作戦の待機所として」(
証言②前田義夫さん)、「久能海岸での戦闘用」、「敵の上陸を阻止できなかった場合に、(山あいなどで)迎え撃つため」などの証言があった。また、駐屯地での待機中に「対戦車肉弾攻撃」訓練をしたという証言を幾つか得られた。「肉攻」すなわち、兵士が急造爆雷を抱えて敵の戦車の前に飛び込む自爆攻撃が戦法として最も重視されたからである。
しかし、6月20日の空襲で火の海になった静岡市街を見た若い兵士は、「この戦争に勝ち目はない」と思ったという。7月7日には清水が空襲され、連隊本部の一部も焼失する。その連隊本部が置かれた国民学校を3月に卒業したばかりの少年は、軍隊は学校に残り、子どもと先生があちこちに疎開しなければならなかったことに胸を痛めたと証言している(証言①服部禎之さん)。有度山には、この時期に作られた壕が数多く残っている。
静岡地区でも用宗・城山などで名古屋師管区歩兵第2補充隊が壕を掘り、長さ300メートルのトンネルが貫通したという証言が得られた。
そのころ大本営は、「各総軍の作戦は沿岸で終わり、沿岸要域の決戦で敗れた総軍はその沿岸要域において玉砕する」という決号作戦の構想を徹底するよう第1・第2・航空総軍に通達する。7月17日の「第1総軍決号作戦計画」によって第13方面軍の作戦も「水際撃滅作戦の徹底」と「御前崎方面の重視」の2点を中心に変更され、8月7日に方面軍司令部に各兵団参謀長等が集まり示された。県内の各部隊も大小の移動が行われている。陸軍が空白であった御前崎方面には新設の独立混成第119旅団を配備し、独立混成第97旅団を藤枝に移駐させた。しかし、第一線の部隊に玉砕を強要した大本営は、長野県松代への移転準備を着々と進めていた。
また清水地区に5月の第3次兵備により新設された独立混成第120旅団(通称「東天部隊」)が配置されつつあった。旅団司令部は庵原村に置かれ、兵力は6,200名とされた。しかし、人員・兵器の不足から部隊の編成は遅れた(欠員・欠数のまま7月26日編成完結)。8月に入隊した兵士経験者から、軽機関銃中隊だったが銃は無く、模擬銃で訓練を受けたという証言を得た。高部村には住民とともに鳥坂山で陣地構築をする東天部隊についての証言も残る。
同じころ護古部隊の第3大隊は、瀬名・鳥坂・高部・飯田・庵原などに広く展開していた。東天部隊の編成に伴い、護古部隊は浜松地区・天竜川左岸の見付へ移動する計画であったが、清水で終戦を迎える。庵原村で訓練中であった東天部隊の兵士の周辺では、護古部隊が陣地構築を行なっており、「護古部隊は陣地構築の部隊、東天部隊はそこに行って守る部隊」と聞いたという証言を得た。
第一戦の部隊では8月15日午前中まで「本土決戦」の準備は進められた。そして終戦後の9月15日、第143師団(護古部隊)の各歩兵連隊旗は、師団長・幕僚立会いの下で焼却された。
終戦時の静岡支隊 防衛省防衛研究所戦史研究センター所蔵
『大東亜戦争 第13方面軍 兵力配備要図(於昭和20年8月15日現在)』より抜粋

一方、三保には海軍の特攻艇「震洋」(ベニヤ板でできたモーターボート)の出撃基地が作られた。第1特攻戦隊隷下で本部を沼津・江之浦に置く第15突撃隊は、第136震洋隊を三保に配備する。ただし、配備された震洋は5隻だった。震洋の格納庫を造った海軍飛行予科練習生15期の少年兵経験者(
証言④横山健治さん)によれば、6月予科練が解散になった後は、敵艦が駿河湾に入ったときに攻撃を加えるということで、終戦まで日本平で砲台の構築に当たり、その後8月23日に復員するまで静浜で飛行機の解体作業を行なったという。
第15突撃隊の基地
歴史教育者協議会編 『幻ではなかった本土決戦』 より

2-3 戦場の住民 ― 国民義勇隊と学徒隊 ―
住民の動員については、5月中に、県知事を隊長とする「静岡県国民義勇隊本部」、7つの「市国民義勇隊」、290の「町村国民義勇隊」等の地域義勇隊が結成されたのに次いで、7月までには167の職域義勇隊が設けられた。6月18日浜松、20日静岡、7月7日清水で出動命令を受けた義勇隊は、空襲後の炊き出し、救護、死体収容、道路等の後片付けに従事した。知事は、国民義勇隊について「最後最終の国民組織であり、戦争に必要なことはなんでもやってゆく」と述べている。
国民義勇隊の編成に照応して、5月には「戦時教育令」が公布され、主に学校単位で「学徒隊」が組織される。すでに3月の「決戦教育措置要綱」によって、国民学校初等科を除く全ての学校の授業が1年間停止されていた。
両者は県の防衛施設の建設にも動員された。7月10日に東海軍管区の要望による「敵上陸ノ場合、軍隊及軍需品運搬ノ為」の作戦道路としての緊急道路(二俣~静岡)が、7月20日には「戦闘義勇隊ノ特攻基地」となる横穴防衛地下施設(総延長15,000メートル)が建設され始めたという。
軍の陣地構築などの土木工事に動員されたのも国民義勇隊や学徒隊だった。有度山での陣地構築については、由比町「勤労動員関係書類綴」に国民義勇隊の「有度地区」「護古部隊」「国防土建作業」への出動命令記録が残る。清水中学(現清水東高等学校)などの生徒も「決戦壕掘り」と呼ばれていた陣地構築に動員された。兵士が掘り出した壕の土砂を二人一組になり天秤棒でモッコを担ぎ、離れた場所に捨てに行ったという。「野砲に使う」というトンネルを掘った生徒もいる。さらに別の証言では、「角材を運ぶ労働だった。平澤観音付近の壕の一つは、曲がりくねったトンネルがいくつも分岐されていて迷路のよう。偶然入り込んだ10畳ほどの空間には四角い窓(銃眼)があり、右に谷津山、左に八幡山、静岡の中心地が目前に広がっていた」という(証言⑦植田勤之助さん)。生徒たちの中には「駿河湾からの米軍上陸に備えて、全山をトーチカ化する」という構想を聞かされた者もいた。
住民への動員要請については、町内に動員数を割り当て、順番で家ごとに壕堀りの手伝いを出した。男たちの多くは出征しているので、ほとんどが成人女性だったが、家の農作業を手伝う少女が行くこともあったという。(証言⑤斉藤サツキさん)家によっては庭木まで供出して陣地構築に協力したが、空襲の時、施設への立入は許されない場合が多かった。また、戦後落盤による被害者も出ている。第143師団(護古部隊)参謀の戦後の回想では、陣地は予定の3分の1が構築されたという。労働力としての動員や私有地の軍用転化の合法化など、基地・陣地の設営が住民の生活に与えた影響は大きかった。
しかし、アメリカ軍は結局のところ、「静岡県への上陸計画」を全く考えていなかった。
静岡県下で「私も壕を掘った」「壕を掘った人を知っている」という方は、当センターにご一報ください。
また証言など、もう少し詳しくお知りになりたい方は、冊子にまとめてありますので、当センターへお問い合わせください。