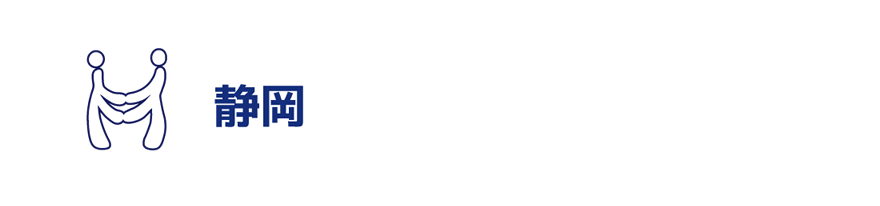今年初めて、「空襲・戦災を記録する会全国大会」が静岡を会場に開催されることになりました。
「静岡平和資料館をつくる会」からの報告もあります。どうぞ、ご参加ください
第54回空襲・戦災を記録する会静岡大会「空襲を描く」
― 世代をこえて描かれる戦争 ―
◆日程概要
8 月 23 日(金)18:00 ~ 21:00(予定) 空襲資料研究会
8 月 24 日(土)09:00 ~ 11:30(予定) 空襲資料研究会
8 月 24 日(土)13:00 ~ 17:30(予定)
13:00 記録する会代表あいさつ
静岡大会実行委員長あいさつ(阿部聖さん)
13:10 ~ 14:40 静岡からの報告
1:静岡平和資料館をつくる会 代表あいさつ(鍋倉伸子さん)
2:会の歩み (田中文雄さん・静岡平和資料センター センター長)
3:静岡県内への空襲の実態 (奥脇卓也さん・静岡平和資料センター 調査研究部)
4:資料の水難レスキュー活動報告 (田中文雄さん・静岡平和資料センター センター長 NPO 文化財を守る会)
5:会と体験画 (田中文雄さん・静岡平和資料センター センター長)
14:40 ~ 14:50 休憩(書籍販売)
講演・シンポジウム 「 空襲を描く― 世代をこえて描かれる戦争 ― 」
講演
14:50 ~ 15:25 おざわゆきさん(漫画家)「空襲を描いた漫画家の話を聞いてみよう」
シンポジウム
15:25 ~ 15:45 佐藤陽子さん(仙台・空襲研究会)「仙台空襲体験の聞き描き」
15:45 ~ 15:50 休憩
15:50 ~ 16:25 井上裕之さん(文教大学・元 NHK)「『戦争体験画』の視点から
16:25 ~ 17:30 質疑応答
8 月 24 日(土)19:00 ~ 21:00 懇親会(※要申し込み)静岡駅近隣を予定
8 月 25 日(日)9:00 ~ 12:30(予定) 各地の活動・自由報告
◆対面方式会場(現地参加は申込先着 80 名様まで)
静岡県男女共同参画センター「あざれあ」 https://www.azarea-navi.jp/
〒 422-8063 静岡市駿河区馬渕 1 丁目 17-1 TEL:054-255-8440
【アクセス】
・対面参加:徒歩または公共交通機関のご利用をお願いします。
※静岡駅から徒歩 10 分
◆オンライン方式参加:Zoom 使用(参加申込者には後日 URL を送付します)
◆1)対面方式で参加費支払いについて
今年、静岡会場で参加される方は、参加申込後、下記の表①〜③の合計額をお振込みください。
振込期間 2024 年 7 月 1 日(月)~ 8 月 20 日(火)
なお、Zoom 参加のかたは Peatix 申込での決済となります。
① 参加費 2,000 円 8 月 23 日(金)~ 25 日(日) 1日のみの参加も3日間の参加も同額です
② 懇親会 5,000 円 8 月 24 日(土)会場は後日お知らせします(静岡駅近隣を予定)
③ 寄付 1,000 円 /1 口 お気持ちに合わせた口数でご寄付をお願いいたします。
<振込先> ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行から 通常貯蓄口座 記号 18120 番号 43450351 佐藤 陽子
他行から 店名 八一八 店番 818 口座番号 4345035 佐藤 陽子
申込内容・振込み確認後にメールで①②③の領収書をお送りいたします。
佐藤 陽子 / E-mail:s.torihito.t@gmail.com
◆2)Zoom 参加の支払いについて
Peatix(クレジット)での支払いとなります。
お申込みはこちらから↓
書面によるお申込みをしたい方は、お問い合わせください
メール shizuoka-heiwa@nifty.com
または fax 054-271-9004(担当・佐野)
空襲・戦災を記録する全国連絡会議 ↓こちらからも概要をご覧いただけます
https://kushusensai.net/